会社員をやめて起業、法人化してひとり社長に──と考えたとき、まず気になるのは「お金」のことではないでしょうか。
会社員であれば毎月の安定した収入がありますが、ひとり社長になった場合のいわゆる「手取り」がわからず、不安を覚える人も多いでしょう。
私自身、ひとり社長になる前は同じように漠然とお金の不安がありました。
しかし実際に法人化に踏み切ることができたのは、ひとり社長になった場合の法人からのお金の引き出し方を、戦略的に組み立てることができたからだと思います。
いわゆる「基本給」にとらわれるのではなく、社長の手元にどうお金を引き出すかのほうが重要だと感じています。
会社員のころと比べて基本給の部分は微々たるものですが、それでも生活に困窮しているわけではなく、会社員時代とほぼ変わらない生活を送っています。
この記事では、会社員とひとり社長の給与のちがいを整理し、見た目の給与額ではなく“実際の生活感”から見えるちがいを実例をまじえて解説します。
会社員時代とのちがい|給与の「基礎」と「可動部分」
私の会社員時代の給与構成は基本給+残業代で、圧倒的に基本給部分が大部分を占めていました。
会社としても残業は極力しない方針だったため、+αにあたる残業代はほとんどありません。
+αは少なかったものの、毎月ほぼ同じ金額が支給され、安定感は抜群でした。
一方で、ひとり社長となった今は、給与の構成は役員報酬+出張手当になっています。
会社員でいうところの基本給が役員報酬で、その他の+αにあたるのが出張手当です。
会社員時代は税金や社会保険の計算の基礎となる所得が給与のほぼ全てでしたが、今は役員報酬のみがその基礎となるというのが最大の違いです。
いわゆる「手取り」は狙った額になっていて、実際に使えるお金も想定と大きくずれていません。
ここでは、私自身がどう考えて給与を組み立てているかを整理していきます。
会社員時代|毎月固定の基本給+α
前述した通り、会社員時代の給与は基本給が中心で、毎月ほとんど変わりませんでした。
残業代はきちんと支払われる会社ではありましたが、そもそも会社全体で「できるだけ残業をしない」という方針だったので、
実際に残業することははほとんどなく、当然残業代が支給される月の方が圧倒的に少ない状況です。
良くも悪くも毎月の支給額はほぼ固定されていると言っても良いくらいで、なんなら給与明細を見なくても支給額がわかるような状況でした。
給与構成は「毎月固定の基本給+α」ではありますが、実際のところ“+α”はないに等しく、毎月固定の基本給=支給額だったのです。
毎月給与明細を見る楽しみはありませんが、給与額の変動要素はないのは生活をする上では安心感がありました。
今|役員報酬4.5万円+α
ひとり社長となった今も、毎月固定されている部分に+αがあるという給与の構成そのものは変わりません。
会社員時代の基本給にあたるのが役員報酬の4.5万円、+αにあたるのが出張手当です。
「基本給4.5万円!?生活できない!」と思う方もいるかもしれませんが、ひとり社長となった今、給与の大部分が+αなのです。
基本給>+αだった会社員時代とは逆に、今は基本給<<<+αになっており、給与構成の比率が大きく異なります。
この+αがあるのは、旅費規程を整え、訪問や外出がある日に出張手当を支給できるようにしているからです。
ちなみに、ひとり社長とはいえ会社役員にあたるため、残業という概念はなく、当然ながら残業代もありません。
出張手当で大半を支払うメリットはいくつかありますが、給与面では出張手当が課税されないという点が大きいです。
通常、給与から社会保険料や所得税が差し引かれて手取りが決まりますが、社会保険料や税金の計算の基礎となる収入に出張手当は含まれません。
どれくらい訪問や外出(=出張)が定常的にあるかを事前にシミュレーションして出張手当を設定したこともあり、「手取り」はおおむね狙った金額になっています。
もちろん、訪問や外出がなければ手当は支給されず、手取りは減りますが、良い意味で営業や対応のモチベーションにもつながっています。
役員報酬はなぜ4.5万円なのか、出張手当とは何か──という点については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
続きを見る

ひとり社長の給料はこう決めた!|訪問型サービスを展開する私の場合
「給与」と「使えるお金(可処分所得)」は違う
会社員の手取りの基本は、[(基本給+各種手当)ー(社会保険料+所得税)=手取り]だと思います。
給与体系や手当の支給基準を自分で決めることはできないので、「引かれるものは仕方ない」と受け止めるしかありません。
もちろん、会社員時代の私もそうでした。
しかし、ひとり社長になると給与体系や手当の支給基準を自分で決めることができます。
かならずしも基本給を高くすることだけが手取りを増やす方法ではなく、手元に残るお金をどう設計するかは、制度の理解と組み合わせ次第です。
私の場合、報酬は最低限に抑え、旅費規程を整備して出張手当を支給しています。
たとえば、基本給が20万円の場合と、役員報酬4.5万円+出張手当の合計が20万円の場合では、いわゆる手取りは圧倒的に後者の方が多くなります。
これは、社会保険料や所得税の計算の基礎とならない部分が多いためです。
会社員時代はいわゆる「額面」の2割減が手取りという感覚でしたが、今は給与から控除される社会保険料が1.1万円程度に抑えられています。
結果として、見た目の給与額よりも実際に使えるお金=可処分所得は大きく、生活水準を下げることなく日常を送ることができています。
法人のルールに従う「会社員」と、ルールづくりから行う「ひとり社長」
会社員とひとり社長の大きな違いは、給与の「決まり方」だと思います。
会社員は会社が定めた制度のもとで給与が支給され、自分でその仕組みを変えることはできません。
一方、ひとり社長は自ら報酬額や手当の設計を行い、税金や社会保険料の負担を見越して制度を整える立場にあります。
ここでは、給与を「決められる側」から「決める側」へと移ったことで見えてきた変化を整理します。
会社員は「決められた枠の中」で給与が支払われる
会社員の給与は、会社が定めた等級や職務の範囲内で支払われます。
支給額の根拠は人事制度や就業規則に明記されており、昇給・賞与の基準もすべて会社が決める仕組みです。
基本給や手当の金額を自分で変えることはできず、昇給のためには会社のルールに沿った評価を受ける必要があります。
また、評価されたからといって、必ずしも自己評価どおりになるわけではありません。
ルールがしっかりしている分、給与は安定していますが、その反面、働き方や成果をどれだけ工夫しても、制度を超えて大きく動かすことは不可能です。
給与の仕組みを自分で動かせないという点では、会社員は「決められたルールの利用者」です。
今でこそ「会社員時代に時短勤務したらこれくらい」という額が手取りになるよう制度設計していますが、正直なところ、制度を設計するという発想自体、会社員時代に持ったことはありませんでした。
ひとり社長は「制度設計」から関わり、収入を決める
繰り返しになりますが、ひとり社長になると、給与の「仕組み」を自分で設計する立場になります。
役員報酬の金額、支給方法、手当の種類などをどう組み合わせるかで、手元に残るお金も大きく変わってきます。
それまで税金と聞くだけでげんなりとしてしまっていましたが、手元に残るお金が大きく変わるとなれば、そうも言ってられません。
私の場合、まずは役員報酬は所得税がかからない最大値にすることにしました。
そうなると、役員報酬は自ずと4.5万円になります。社会保険料は引かれるため、手取りは3.3万円程度。もちろん、これだけでは生活ができないので手取りを増やす工夫をしなくてはいけません。
そこで活用しているのが旅費規程です。うまく使うと、事務の手間を簡略化できるだけではなく、手取りを増やすことができます。しかも非課税。
私の手取り設定のターゲットは「会社員時代に時短したときの給与の手取り」だったので、そこから3.3万円を引いた額程度が旅費規程に基づいて支給されれば狙い通りです。月の平均的な出張回数や一般的に支給される額などを調べた上で出張手当を設定し、出張回数に応じて手当が上乗せされていく設計になっています。
私にとって、税金や社会保険料の仕組みは複雑怪奇なものですが、報酬体系はその影響を考えながら組み立てる必要があります。税金の仕組みを勉強したり、プロである税理士さんにも相談しながら制度設計していきました。
収入の大半を出張手当で補填する私のようなやり方は、相手先に訪問するような事業の方が向いています。
お客様に来ていただくタイプの事業の方は、このやり方では会社からお金を効率的に引き出すことはできないので、税理士や会計士などの専門家に相談することをお勧めします。
給与の決め方については、こちらの記事も参考にしてください。
続きを見る

ひとり社長の給料はこう決めた!|訪問型サービスを展開する私の場合
経費と手取りの境界を理解して生活設計に活かす
「会社員時代に時短勤務にした時の手取り」になるように制度設計をしていますが、その大部分は出張がなければ支給されません、当然、実際の手取りは「会社員時代に時短勤務にした時の手取り」より少ない月もあります。
それでも生活できているのは、会社員時代には個人で支払っていた支出の一部を、法人の経費として処理できるようになったからです。
たとえば、通信費。会社員時代は携帯もインターネットも当然ですが個人負担です。携帯は社用携帯として利用していて経費は法人が負担しています。インターネット代も法人と私個人との間に賃借契約を結び、法人で一部負担しています。
その他大きなものは、ガソリン代や保険代を含む車の維持費全般は法人持ちです。
明らかに事業で使うものについては、法人の立ち上げに併せて私個人から法人へ売却し、客観的に見ても法人の経費として処理するのが妥当な形にしています。
個人から法人への資産売却についてはこちらの記事で私のケースを紹介しています。
続きを見る
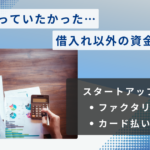
あの頃知っていたかった…借入れ以外の資金繰り方法
このように、もともと個人で支払っていたものが法人持ちになれば生活に必要なお金はその分減ります。そうなれば、自分の「手取り」が減ってもこれまで同様、生活はできるのです。
もちろん、すべてを経費にできるわけではなく、私的利用との線引きは常に意識する必要があります。
それでも、経費として計上できる支出があることで、限られた手取りでも生活の見通しを立てることが可能です。
社会保険料が低いとどうなる?|将来の保障とのバランスを考える
ここまで読んで、「社会保険料を減らせば手取りが増える!」「とにかく社会保険料は低くすればいいのかも」と思った方もいるかもしれません。
では、社会保険料が低いとどうなるか、考えたことはありますか?
ここでは、社会保険料を抑えることによってどんな影響があるか整理してみます。
社会保険料を抑える=公的保障を減らすということ
社会保険料を低く設定すれば、毎月の負担は確かに軽くなります。私もはじめは、「社会保険料を低く抑えることができる」ということばかりに目がいっていました。
しかしその分、将来受け取れる年金が減ることに気付いてしまったのです。
かなり高い社会保険料を納めていたとしても年金支給だけで安心して老後を過ごすことはできないのに、社会保険料を低く抑えれば、将来の保障を自ら小さくすることになるのです。
「今まさに」手取りを増やす方がいいのか、将来の保障をなるべく大きくするのか。どちらを重視するかも設計のタイミングで考える必要があると思います。
給与の仕組みを設計する際は、税理士だけでなく、社会保険・労働保険の専門家である社労士にも相談してみてもいいかもしれません。
社会保険料を抑えるなら自己防衛が必要
社会保険料を低く抑えると、将来の保障はその分減ってしまいます。
だからこそ自分で準備する必要があります。つまり、「自己防衛」が欠かせません。
私自身、将来の保障のために活用しようと考えているのが、小規模企業共済とiDeCo+です。
もちろん、「とにかく手取りを最大化してNISAで運用する」という考え方もあると思います。
私もそうですが、創業期などは特に資金繰りが厳しい時期なので、社会保険料を抑えることばかりに注目しがちです。制度を作る側になったからこそ、その先のことまで見据えておく必要があると感じています。
まとめ|設計で「自由に働ける暮らし」をつくる
ひとり社長になって感じるのは、「手取りの多さ」よりも、自分に合った制度をつくることの大切さです。
会社員のころは、会社が決めたルールに沿って働き、給与が支払われ、それらを自分でコントロールすることはできませんでした。
今は、働き方や給与の構成、経費の使い方など、働く上でのあらゆるルールを自分の暮らしに合わせて組み立てることができます。
もちろん、自由には責任が伴います。
それでも、自分の暮らしを踏まえて設計したルールだからこそ、無理なく働くことができます。
会社員時代のような「与えられた安定」はないかもしれませんが、無理なく続けられる制度を自分で整えられる今のほうが、ずっと満足度は高いと感じています。

